



古代文字「縄」
『字統』より一部抜粋。
旧字は「繩」。後漢代の『説文解字』では、「索(なは)なり」とあり、大なるを索、小なるを繩という。縄墨(じょうぼく・すみなわ)の意があり、それより度流・法る(のっとる)・戒める・正すと訓する。…とあります。
Blogお伊勢参り、
昨日はようやく内宮のご正宮に到達したけど、サラッとネットでわかる情報だけでまとめて、スピスピ寝てしまいました。
一昨日の外宮の正宮もそうでした。
今一つ消化不良だったなと思いながら、今日、研究室の片付けをしていたら、書架からパラパラと天照大御神と大祓祝詞のレジュメがっ…!!
不思議なことってあるものです。
もうちょっと私のこと勉強して💢って天照大御神さまと豊受大神さまに言われたような気がしました。
いずれまた改めて神宮式年遷宮のことなども書いておこうと思います。
今日は、Blogお伊勢参りの最終ポイント!?スサノオノミコトです。
スサノオノミコトは天照の弟神です。
出雲大社には「素鵞社」(そがのやしろ)があり、スサノオノミコトがお祀りされています。
さすがにスサノオは伊勢では出番が少ないだろうと思っていたら、なんと、『備後国風土記』の「蘇民将来」の逸話によってスサノオノミコトが伊勢のまちにあふれていることに気がつきました。これに気がついたのは、赤福餅を食べに行った時、蘇民将来の絵本『蘇民将来守りの木札』が置いてあったからです。赤福行ってよかったです!
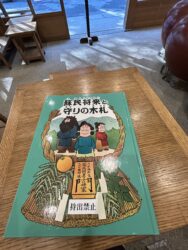
絵本『蘇民将来守りの木札』



伊勢では1年中「伊勢型」と呼ばれるしめ縄を飾っていますが、そのしめ縄の特徴は、正面に伊勢地方の特徴となる檜の木札があり、木札の中央に「蘇民将来子孫之門」と文字が書かれていることです。
Blog.25でも紹介しましたが、「蘇民将来」の逸話はこんなお話しです。
スサノオノミコトは伊勢を旅している時、ある兄弟に宿を求めたところ、豊かだった弟は断りました。一方、兄の蘇民将来は、貧しかったのにスサノオノミコトを栗や粟酒で温かくもてなしました。その後に疫病が流行った時、スサノオノミコトは蘇民将来の恩に報いようと、蘇民将来やその娘らに腰に茅の輪をつけさせることで家族を救いました。さらに、説話の中で武塔神(スサノオノミコト)は、今後、悪い病気が流行したら除厄の呪文として「蘇民将来の子孫」と唱えるように言います。
これが伊勢型しめ縄の由来になっている「蘇民将来」の逸話です。
やっぱり伊勢の人々もスサノオノミコトが大好きなんですね。
この伊勢型のしめ縄は、伊勢地方の店舗をはじめ一般のお家でも年中飾っているので、伊勢に行けば普通に目にするものですが、木札に「蘇民将来子孫之門」と書いてあることを意識してみたことがなかったので、なんと今回まで伊勢地方のしめ縄とスサノオノミコトとのつながりに気が付いていなかったのです。恥ずかしいです。
ちなみに、スサノオノミコトを御祭神として祀る須賀神社では「大祓」の神事とともに「茅の輪くぐり」が大切な行事の一つとなっていますが、下の写真のような茅の輪もしめ縄のひとつです。

四谷須賀神社(2024年12月31日撮影)

須賀神社の幟旗「蘇民将来子孫也」
茅の輪くぐりの期間のみこの旗が立てられています。
神社用のしめ縄を製作販売している折橋商店という会社のサイトには、しめ縄のお話がとてもわかりやすく掲載されています。それによると、「しめ縄」の歴史は古く、昨日のBlogで紹介した天照大御神の「天岩戸」神話まで遡ります。
先日も紹介しましたが、スサノオノミコトがやんちゃすぎて困った天照が岩戸に閉じこもり、世の中が乱れた時、神々はなんとか天照が岩屋から出てくるように手を尽くしていました。
天宇受売命が神楽を舞い、その姿に神々が喜び笑ってどよめいだ時、天照が何事かと少しばかり岩戸をあけました。そこですかさず、手力男命(あめのたぢからお)が外へ連れ出し、二度と岩戸に入らないように縄を張りました。
これがしめ縄のはじまりとされています。(『古事記』では「しりくめなわ(尻久米縄)」)
しめ縄は、その後、さまざまな地域で歴史と共に多様な意味を帯びています。
神域と俗世間とを区別し、不浄なものが神域に入るのを防ぐ結界としての意味や、奈良時代の『万葉集』では「標縄」とあり、神の存在を表す目印として掲げた縄の意味がありました。
平安時代の書物では「注連縄」と書かれています。「注連縄」は「葬送のとき、死霊が帰ってきて家に入らないようにするために、出棺のあと門戸にしめ縄をひきわたす」とあり、「注連」は死霊や亡鬼の侵入を防ぐために家の入口に「水を注いで連ね張る縄」との意味があるそうです。

出雲大社の神楽殿(本殿ではありません)
他にも神の場や聖域を示す「占縄」「〆縄」や、陰陽道において陽数とされる753「七五三縄」で神聖な場所に陰の気が入らないように封じたり、神社だけでなく、御神木や巨石、滝、岩などの自然物にもつけられている場合が多いです。二見興玉神社にある夫婦岩には太い大しめ縄が張られています。先ほど書いた大祓の茅の輪(ちのわ)もしめ縄の一種で、輪のしめ縄をくぐることで、穢れを落とします。

二見興玉神社の天の岩門(夫婦岩)の大しめ縄

二見興玉神社の「輪注連縄」(禊祓)
身体の良くないところを輪注連縄でさすってお供えします


お正月のしめ飾りは、歳神様をお迎えする準備であったり、家の中が清浄であることを示す迎えの目印であったり、神様がいらっしゃる依代(よりしろ)を示したりするほか、家に邪鬼が入るのを防いて、神々と住む人々を護る呪具の役割もあります。また、お正月のしめ飾りは玄関だけでなく、かまどや井戸、蔵、台所、車などにも災い除けや日頃の感謝、神様の依代として飾る地域もあります。
金運💰✨のフラワーエッセンス👏

神様方はおいそがしいので、
今夜のお茶は、ルイボスティー💓入り
免疫力を高め、風邪を予防する効果。
ポリフェノール、マグネシウム、カリウム、ルチン、フラボノイドなどが含まれています。
今日もすごく豊かなものをたくさんいただいて感謝✨
情報源
三重県総合博物館公式サイト「伊勢地域の「しめ縄」
https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/83003046690.htm
「蘇民将来」の説話についての情報源 上田市デジタルアーカイブポータルサイト「「備後国風土記」の蘇民説話」より)https://museum.umic.jp/somin/sominshou/s_sominshou02.html
(株)折橋商店(神社用しめ縄販売)
https://orihasisyouten.jp/